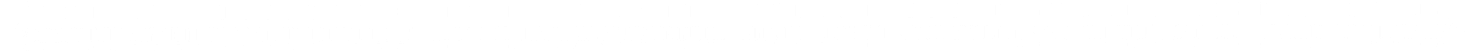 なんの問題もなかった。最初から、エデンへやってくるその前からそのつもりだった。むしろ、こんな展開は残虐な殺人鬼にとってもったいないくらいのハッピーエンドと言えるだろう。
なんの問題もなかった。最初から、エデンへやってくるその前からそのつもりだった。むしろ、こんな展開は残虐な殺人鬼にとってもったいないくらいのハッピーエンドと言えるだろう。友と呼んだ死体の怨嗟が、頭の中に響いている。その怨嗟を、もう縦に振れる首もないが、うん、うんと肯定する。
俺を裁くのは神ではなく、友であった。勝手に殺し犯した相手を未だ友と呼ぶのはとんでもないとは思うが、ともかく俺はまだそう思っているし、もう死ぬ身であるのだからそう思っても誰の迷惑にもならないだろう。
隣を見る。スピネルが笑っている。涙を流しながら、それでも幸せそうに俺と共に落ちていく。彼女を笑顔にさせることができたのが、俺ではなく友であったのは少しだけ悔しい。
俺は幸せものだな。バラバラになった死体の首は、もはや死後特有の痙攣しかしないだろうに、そんな風に喋ったように見えた。
雷が鳴っている。嵐の夜、クラアナへ2つの死体が落ちていく。ひとつはクラアナとエンドボードの間に落ち、もうひとつはクラアナの奥深くへと消えていった。
――――
――――
――――
「薔薇をたくさん集めてさ…。君に送るよ。100万本くらい、たくさんの花束を」
それを聞いた女はキョトンとして、ティーカップをソーサーの上に置いた。白地に金の装飾が施されたティーカップ。そこに、給仕キカイが新たな紅茶を注ぎ入れる。テーブルを共にしている大男は、いかにも夢見がちな、うっとりした顔で青い空を眺めていた。空と同じ輝くような青色の前髪が、風になびいてゆらゆらと揺れる。
花々が咲き乱れる庭園に、一組の男女がいた。ひとりは大きなリボンのついた婦人用ボンネットを被りドレスを着た、長い赤髪のいかにもなお嬢様。もうひとりは、青い短髪とスーツをピシッと整えた、身長2mはあろう恵まれた体躯の御曹司。もっとも、今その御曹司はうっとりとした顔で頬杖をつきながら背を丸めているために、威厳なんてものはまったく感じられないのだが。
「そんなの、お金の無駄遣いよ。アクアはロマンチストね」
「一生に一度の結婚式なんだ。それくらいしたってバチは当たらないよ。そうだ、俺とスピネルの髪色に合わせて、青と赤のバラを用意するのはどうだろう。きっと、きれいだよ」
「青のバラなんてどこにあるのよ。ほら、目を覚まして。もっと現実的な目線で予定を組まないと、みんな困っちゃうでしょ!」
「いててっ」アクアと呼ばれた男が、頬を引っ張られて目に涙を浮かべる。
ふたりはいつもこうだった。ロマンチストな御曹司としっかりもののお嬢様。物語で語られるような、お似合いのふたり。下層を知らず、上層だけが生きる世界のすべてという、絵に書いたような上級市民。
ここはダイア。遠く離れたエデンよりは小さいが、それでも人々とキカイが共に生きる居住可能都市。その最上層に、ふたりは暮らしていた。すべてはより空高くにいるキカイの庇護下であったが、生まれてこの方不自由を感じたことのない上層の民はキカイを良き隣人と信じている。
「アクアマリン様」
頬を引っ張られるアクアに声をかけるキカイがひとり。メイドの服を着た、侍女キカイだ。
「今月の下層への寄付の件ですが」
「ふにゃ、オーダー……」キカイの名前を言うと、スピネルに頬をぱっと離される。頬をさすりながら返事をした。「いつもどおりで大丈夫だよ。俺の資産の三分の一を送って」
「それが、暴走キカイの被害が多く、寄付金ではすべて賄えないと下層民から……」
「ほら!」スピネルが言う。「みんな大変なのよ。最近は暴走キカイも増えて持ち帰れるシザイも減っていると聞くわ。下層民だけじゃなく、探索者にだってもっと支援しなきゃ。私達だけ贅沢しているわけにはいかないのよ」
「わ、わかったよ…」
そう言って、アクアはオーダーの持っていた書面にサインをする。資産の二分の一を寄付するという内容だ。
ふと、遠くの地にあると聞くエデンという居住可能都市に想いを馳せる。エデンには、神様と、暴走キカイから人々を守る巨大なキカイがいるらしい。きっと、とても住みやすい場所なんだろうな、と夢想しながら
「夕食の七面鳥を一匹減らさなきゃいけないな…」
そう、のんきにつぶやいた。
「じゃ、私はおやつのドーナツを減らそうかしら」
「なら、俺は更に昼食のスープも減らすよ」
「ふふ、えらいえらい」
スピネルがアクアの頭へ腕を伸ばす。アクアはかがんで、頭をなでやすい高さへ持っていく。整った髪型が乱れるのも気にせず、うれしそうになでられつづける。花の庭園にふたりの笑い声が響く。幸せだけが彼らを包んでいる。
――――
本当になにもしらない、典型的なまぬけの金持ちだ。
コメディ映画だったら大爆笑が取れるだろうよ。こいつは大金を出すが、その金が実際にどこへ流れるかなんて知らないんだ。無知は罪だとよく言ったものだ。
――――
「キャアッ!」
夜、寝室に入ってきたアクアはなんともマヌケな悲鳴をあげた。眼前にはベッドに座るスピネル。美しい長髪をリボンでふわりと束ねて……。それはいつものことだ。それよりも問題は――
「この映画そんなにこわい?」
スピネルが見ていたのは映画だ。旧時代の娯楽、豊かな文明を示唆する映像作品。そんな貴重な情報が詰まったデータだというのに、肝心の中身は血みどろの殺人鬼が暴れ狂う残虐なものだった。
「消して消して! ……ふぅ、びっくりした」
「アクアは怖がりね。ただの作品よ。ほら、最後にはNG集もある」
スピネルがモニターに指をかざすと、その内容は殺人鬼と被害者が笑い合うエンディングへと変わる。
「それすら、俺には悪趣味に見えるけど……。スピネルは本当に怖い映画が好きだね…」
「だって、刺激的じゃない!」
アクアが隣に座ると、スピネルがくるりとアクアに向かって目を輝かせる。スピネルは昔からこういったものが好きだった。お嬢様にあるまじき、過激な趣味。いいや、こういうところも素敵ではあるのだがとぼんやり惚気つつ。
「俺にはわからないな……。あんな血みどろ劇、恐ろしいだけじゃないか」
「たしかに恐ろしいけど……。私ね、憧れるの」
その言葉を聞いてぎょっとしたアクアを、スピネルは笑って訂正する。
「別に誰かをひどい目に合わせたいわけじゃないわよ。ただ、あの主人公たちはあんな地獄の中でも諦めないで歩き続けるの。どんな絶望の中にいても、希望を失わずにいられるのって、とっても素敵なことだわ。地獄にも希望ってあるんだって思うと、私も勇気が湧いてくるの」
なるほど。画面の恐ろしさに気を取られていたが、そう言われれば主人公たちはどんなに痛めつけられようと生き延びようと必死に抗い続ける。ただ、それはそうしないとお話が終わっちゃうからだ。実際は絶望に呑まれて諦めるものだろうよ……と、アクアの喉元にまで出かかって、飲み込んだ。この輝く瞳を曇らせるのは本意じゃない。
「俺としては、あの殺人鬼も何考えてるんだか……」
「それはね!」
スピネルが棚から一冊の本を取り出してアクアに見せる。さっき見ていた映画の殺人鬼が表紙に飾られた、愛蔵版……。愛蔵版?
「彼はね、元々良い人だったんだけどある日妻を殺されてその後の自殺未遂で……」
「わかった。わかった」
「彼は殺人鬼だけど、かわいそうな人なのよ。それに、ちょっと人間臭いところもあってね」
「ううん。スピネル、明日も早いから……」
閉口しながら、ベッドの中へと潜り込む。興味のない事柄を早口でまくし立てられると、いくら愛しい相手でも少しめんどうくさくなる。
「うーん、アクアにこの映画はまだ早いわね」
俺は一体、何歳児だと思われているのだろうか、とアクアが口を尖らせる。しかし、同じくベッドに入ってきたスピネルの体温を感じて顔をほころばせた。そのまま目を閉じようとするが、なんだかバタバタとうるさい。
「スピネル、映画消して……」
「違うわ。私じゃない……」
ベッドから起き上がる。モニターは消えている。それでは、この音は一体……
次の瞬間、窓ガラスを突き破る音。スピネルの悲鳴。防音ガラスが割れて初めてわかる、外の喧騒。
「暴走キカイだ!」
真っ赤に染まったその姿は、まさしくモニター越しに見たことのある暴走キカイそのものだ。実際に目のあたりにするのはこれがはじめてのことだった。咄嗟にベッドから飛び起き、スピネルを守るように暴走キカイと対峙する。
外の喧騒が聞こえてくる。人々の悲鳴、キカイの駆動音。一体だけじゃない。多くのキカイが、この上層まで上がってきている。
「どういうことだ!? 対暴走キカイ用の設備投資はしていたはずなのに…」
「アクアマリン様! 外から暴走キカイたちが突然屋敷に――」
オーダーが慌てた様子で寝室に入ってくる。アクアの視線が暴走キカイからオーダーに向けられる――
「ギッ」
激痛。何が起こったのかわからない。痛む場所に目をやる。腕が、ない。
「ギャアアッ!!」
なくなった腕だけじゃない。生まれてこの方、感じたことのない痛みが全身を駆け巡る。暴走キカイの持つ大きな刃物に血がついている。薄暗い寝室では、自分の腕がどこにあるかわからなかったが、ともかくその刃物で腕を切られたことは理解できた。
「アクア!!」
「ヒッ、ヒィッ……」
自分の腕の骨と肉が見える。血が止まらない。体はすでに過呼吸を起こしていた。末端がしびれ、うまく動かない体をよじり、なんとかスピネルの方向を向く。
「あっ……」
スピネルの腕を、別の暴走キカイが掴んでいる。いつの間に入ってきたんだ。
「アクア! アクア!」
やめろ。やめてくれ。俺たちがなにをしたって言うんだ。
「アクア!!」
スピネルが見ている。体が動かない。俺が立って立ち向かえば、スピネルを助けられる。
「アクアッ……ッ……」
スピネルが見ている。俺は今、立ち上がるべきだ。俺が――
血しぶき。スピネルが俺を見ている。スピネルが、スピネルの腕が、足が、頭が、腸が、乳房が、瞳が、赤く濡れてバラバラに解体されていく。スピネルの髪を束ねていたリボンが宙を舞う。スピネルの血が俺の顔にかかる。スピネルが見ている。
――――
当時は意味がわからなかったが、今考えれば簡単な話だ。横領だ。
俺がきちんと視察に行っていれば、こんなことにはならなかったのかもしれない。それをしなかったのは、ただ恐れていただけだ。俺は忙しいから、下層は怖いところだからと、他人に押し付けて見ないようにしていただけ。
死にたかった。このときからずっと、ずっと死にたかった。
――――
気付いたときには、残った片腕でスピネルのリボンを掴み、クラアナ内部で倒れていた。辺りは暴走キカイと侍女キカイの残骸。
恐ろしかった。恋人と、隣人と信じていたキカイの、むごたらしい死。流れる血と油。敵だろうが味方だろうが、キカイは良き隣人とずっと信じていた。割り切れない。全部、俺が殺したんだ。涙が止まらなかった。
ダイアは一夜にして滅んだ。エレベーターは破壊され、すでに街へ戻ることは叶わなかったが、大きくひび割れたダイアのボードを見て、そう確信した。
しばらく、泥水を飲み探索者の遺品を漁って暮らした。襲いかかってくる暴走キカイを殺すごとに、自分がおかしくなるのを感じた。
時折、思い出したかのように拾ったナイフで体を切り裂いた。それでも、丈夫な体は死ぬことを許さなかった。
――いいや、死ねばよかったんだ。暴走キカイに首をはねられる。高所から落下する。餓死する。どれでも死ぬことはできたはずだ。それをしなかったのは、ただひたすらに死ぬのが怖かったからだ。
それから数ヶ月、探索隊の遺品を漁っていたときのことだった。
「人間、か?」
声がした。暴走キカイではない、生身の人間の声音。
「……キャッ」
突然の出会いで、しばらく使っていなかった声帯がうまく動かず口からは奇妙な鳴き声のようなものしか出なかった。
人間がふたり。背の高い人間と低い人間。そういえば、探索者はバディを組んで探索に挑むものだという。分け前と生存率の兼ね合いのため、だったか。
「下がってろ。汚染探索者だ」
背の高い探索者が言った。汚染探索者とは、一体なんだろう。
背の高い探索者が腰につけた発電機のハンドルを勢いよく引き、大きな丸鋸を駆動させる。意味がわからなかった。とにかく、怖かった。
怖かったから、殺したのだ。はじめての殺人だった。でも、すでにキカイを殺した身の上であったから、特別な感情は湧かなかった。
とっさに足払いを仕掛け、体勢を崩した相手から丸鋸を奪うのは簡単なことだった。
「わああっ」
もうひとりの背丈の低い探索者が叫び、腰を抜かしてその場にへたり込んだ。
血しぶきが顔にかかる。背の高い探索者の頭が割れ、血溜まりを広げていく。
「キャハ、だいじょうぶ、ですか?」
背丈の低い探索者に声をかける。この言葉が適切であったかどうかはわからないが、ともかく相手を威圧しないように、丁寧に。
その声を聞いた探索者の様子は、予想だにしないものだった。
「へ、へへっ、同じ探索者さんでしたか……。いやぁ、親方がどうもすみません」
笑っている。丸鋸の駆動音は止まらない。どうして? おかしいじゃないか。人が死んだのに、へらへらと。
ふつふつと、怒りが湧き上がる。理不尽だとはわかっていても、もう抑えきれなかった。
思い切り、その顔を踏みつける。
「どうして? なんで、人を殺してキカイを殺して、怒らないんですか? どうして、そんなにへらへら笑えるんですか? どうして、こいつは死んだほうが良いって叫ばないんですか!?
おかしいだろ。こんなやつ、生きてちゃいけないだろ。言えよ、くたばれって。苦しんで死ねって。みんなに謝って死ねって言え!!」
心からの叫びだった。何度も何度も踏みつける。手足がバタバタと暴れまわる。そのうち頭が割れて、血溜まりがふたつに増える。
「キャ、キャハ。キャハハハハッ!!」
苦しんで死んだ。もがいて死んだ。
「キャハハッ」
俺は、その死体に自分を重ね合わせる。そうすると、まるで除染キットを使用したときと同じように胸がすいた。これは俺の死体。アクアマリン・ルミナスという男が受けるべき罰だ。
スピネルが見ている。その姿を見つめ返す。俺の瞳にはスピネルの姿がはっきりと映っていて、それはもう現実か幻覚かなんて見ただけじゃ区別がつかない。
俺はスピネルから俺の死体へと視線を戻す。一通り眺めたり触れたりして楽しんだ後、食料と水を探すために荷物を漁った。
「ちがうんだ、スピネル。こいつが悪いんだ」
口から出るのは言い訳ばかりだ。責任をよそへ押し付け、ものを深く考えないほうが楽だと気付いたのは、このときだったか。
スピネルが見ている。彼女が地獄に落ちるような人間ではないことは、俺は誰よりも理解している。俺が俺の身勝手でスピネルを地獄に縛り付けているのを、俺はわかっている。
探索者の荷物の中には、エデンの印が刻まれた手帳が入っていた。エデンへの帰還方法が記された手製の地図だ。
エデンに到着したのは、それから数年後のことだった。地図を持っていても、クラアナを行くのは容易ではなかった。
エデンには神様がいる。神様なら俺を裁いてくれるかもしれない。俺と、スピネルをこの地獄から開放してくれるかもしれない。そう思っていた。
――――
いや、違う。俺のせいじゃない。違う、全部俺が悪い。嫌だ死にたくない。いや、俺は苦しんで死ぬべきだ。頭の中がぐるぐる回って、毎日のように吐いた。
誰か。俺を裁いてくれ。ダメならダメと言って、死刑台に送ってくれ。
俺はいくじなしだから、俺自身を裁くことができないんだよ。誰か、誰か――
――――
脂汗にまみれて飛び起きた。エンドボードはまだ夜の帳に包まれている。隣には自らが汚した死体。エンドボードの屋外で死体とともに寝ようと、何も起きない。だれも、何も言わなかった。遠くで犬人間が遠吠えをする。スピネルがまたこちらを見ている。彼女はなにも言わない。
「ラムくん」
悪夢で乱れた息を整えながら、死体に話しかける。スピネルが見ている。
「ラムくんは、俺のこと……」
死体に触れる。冷めきった死肉の感触が、手のひらへと伝わった。
「キャハ、なんでもないです。ほら、もっとくっつかないと風邪ひいちゃいますよ。もう夜風が冷たい時期ですからね……」
死体を抱き寄せて、再び床に横になる。エンドボードの床は冷たくて、まるで自分まで死体になれたような気がした。
起きたら、また死体を加工場へもっていかねばならない。一瞬、シザイのやりくりを考えて、すぐに頭から消した。
人々が探索者になる理由は本当に様々だ。それは金のためであったり、生存価値のためであったり、はたまた冒険心であったりする。
自殺志願者だっているだろう。
スピネルが見ている。俺のことを心配するように見つめては、涙で手袋を濡らしている。もう何年も、ずっと。
「おやすみなさい、ラムくん」
死体は返事をしない。再び、目を閉じる。
――――
――――
――――
――あぁ、あんな顔をしていたのか。俺の友達は。
ちびり、ちびりと酒場でひとり、ラム酒を飲む。
胸に傷の付いた店員がカウンターの奥へ行くのを見守りながら、俺はカウンター席でひとり、顔が赤くなるような青くなるような、めちゃくちゃな感覚に襲われうなだれていた。これも俗に言うNG集というやつなのか? いや、あれは映画の話だ……。実際は、自分が殺した人間の顔なんて恥ずかしくて申し訳なくて、見ていられない!
もうすっかり頭は晴れたというのに、今度は恥から逃げるために酒で頭を鈍らせた。俺はつくづく情けない男だなと、少しへこたれながら。
ちょいちょいと、横から酒瓶をつつく手がひとつ。
「うさぎさん……」
俺が殺したうさぎの少女が酒瓶を掴もうと手を伸ばしている。とっさに酒瓶を遠ざけて、それを阻止した。酒を飲んでぼんやりしているというのに、腕はパッと動く。
「もう、やめてよね」
すべて、最初からそういえば良かった気もする。後悔ばかりが思い出される。うさぎ少女が今度はもうひとつのグラスに手を伸ばし――それも阻止した。
ぽこっ。やわらかい手でパンチを食らう。
ある意味では、今までのどんな攻撃よりも重いパンチだ。俺はどうすることもできず、まいったと顔を困らせた。しかしラム酒を渡すことはできず、やまない攻撃に一方的にされるがままになる。
「これは俺と彼女のなの……。ダメだって。前に、お酒でおうち燃えてたでしょ」
ぽこっ。ぽこっ。うさぎ少女のやわらかいパンチは止まらない。
スピネルはいない。だが、彼も俺もわかっている。きっと彼女はやってくる。彼女はしっかり者だから、俺が死んだら走って迎えに来るだろう。それまで、ここで待たせてもらうつもりだ。このうさぎ少女からラム酒を守りながら……。
スピネルが来たらなんて言おうか。あの店員にもなにか声をかけるべきだ。この少女にだって――
うさぎ少女のパンチの洗礼を受けながら、俺はみんなへの謝罪の言葉をどう口にするか考え続けていた。






